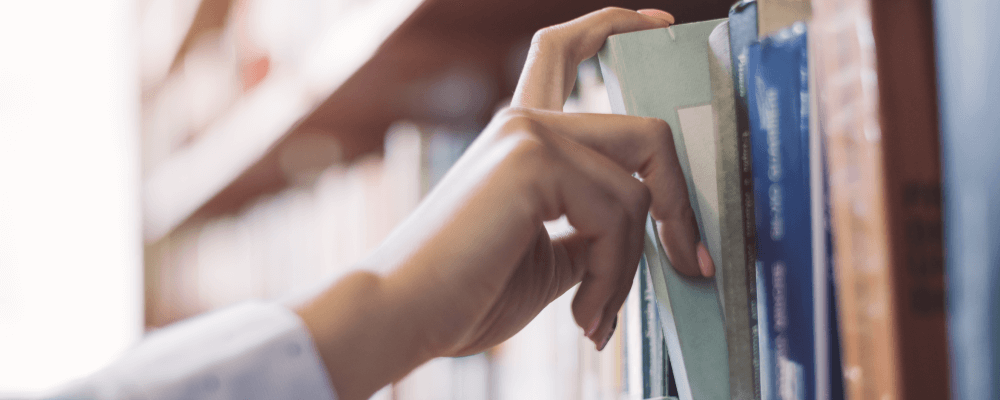財務情報の信頼性を保証する「資本市場の番人」
公認会計士
試験情報
公認会計士は、監査と会計の専門家として、企業が作成した財務諸表やその他の財務情報を独立した立場で監査し、その情報の信頼性を確保する仕事です。「資本市場の番人」ともいわれるほど、社会的に重要な使命を担う存在です。公認会計士が行う監査業務は、高度な専門性が要求されるため、合格難易度は非常に高いものの、高収入が期待できることから人気資格となっています。
公認会計士の試験情報とおすすめの学習方法

公認会計士は、企業などが作成した財務諸表を第三者の立場からチェックして、その情報の適正や信頼性を確保する監査・会計の専門家です。
監査業務は公認会計士しか行なうことができない独占業務で「資本市場の番人」と呼ばれるほど、社会的に重要な使命を担う存在でもあります。
公認会計士になるには、まず国家試験である公認会計士試験に合格する必要があります。
さらに、3年以上の実務経験と実務補習を修了し修了考査に合格して、公認会計士登録と なります。国家試験は、監査業務をはじめ高度な専門性が要求されます。合格難易度は非常に高めですが、その分社会からの評価やニーズは高く、高収入も期待できるので人気資格です。
この記事では、公認会計士試験に関する情報を解説したうえで、おすすめの学習方法についても紹介します。公認会計士を目指している方、国家試験について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
公認会計士の試験情報

国家試験というだけあって細かい制度や規定が設けられているため、あらかじめ把握しておくことが大切です。そこで、国家試験における受験資格や試験日程、試験形式などについて詳しく解説します。
公認会計士の試験制度
公認会計士試験を受ける場合、以下の試験制度は必ず押さえておきましょう。
受験資格
公認会計士試験には受験資格の制限がないため、学歴・年齢を問わず誰でも受験可能です。令和5年合格者の平均年齢は24.5歳ですが、10代後半や60代前半で合格された方もいます。なお、史上最年少合格者は、2010年に合格された16歳の方です。
試験形式
公認会計士試験は「短答式試験」と「論文式試験」の2つに大別されます。
短答式試験
年2回実施するマークシート方式の択一式試験
| 実施時期 | 第Ⅰ回:12月上旬の日曜日 第Ⅱ回:5月下旬の日曜日 |
|---|---|
| 試験科目 | 財務会計論・管理会計論・監査論・企業法 |
| 実施形式 | マークシート方式の択一式試験 |
| 合格判定 |
|
短答式試験合格者は合格発表の日から2年間、短答式試験を免除
論文式試験
科目別の筆記式試験 一括合格以外に、科目合格制度あり
| 実施時期 | 8月下旬(土日を含む3日間) |
|---|---|
| 試験科目 | 必須科目:会計学(財務会計論・管理会計論)・監査論・企業法・租税法 選択科目:経営学・経済学・民法・統計学から1科目選択 |
| 実施形式 | 筆記式試験を科目別に実施 |
| 合格判定 |
|
免除規定
公認会計士試験を受けるにあたり、一定の条件を満たしていると試験科目の一部、または全部が免除されます。おもな免除規定は以下のとおりです。
短答式試験
- 1.税理士となる資格を有する者(注)
→短答式試験(財務会計論) - 2.税理士試験の簿記論及び財務諸表論の合格者及び免除者
→短答式試験(財務会計論)を免除 - 3.大会社・国・地方公共団体等で会計または監査に関する事務または業務等に従事した期間が通算7年以上になる者
→短答式試験(財務会計論)を免除 - 4.専門職大学院において、
- (1)簿記、財務諸表その他の財務会計に属する科目に関する研究
- (2)原価計算その他の管理会計に属する科目に関する研究
- (3)監査論その他の監査に属する科目に関する研究により、上記(1)に規定する科目を10単位以上、(2)及び(3)に規定する科目をそれぞれ6単位以上履修し、かつ、上記(1)から(3)の各号に規定する科目を合計で28単位以上履修した上で修士(専門職)の学位を授与された者
- 5.司法試験合格者
→短答式試験を全部免除
(注)税理士登録が必要です
論文式試験
- 1.税理士となる資格を有する者
論文式試験(租税法)を免除 - 2.司法試験合格者
論文式試験(企業法・民法)を免除 - 3.不動産鑑定士試験合格者
論文式試験(経済学または民法)を免除
(注)税理士登録が必要です
なお、免除科目があるときは、それを除いた科目の合計得点の比率から判定します。
令和7年(2025年)試験日程
令和7年(2025年)度の公認会計士試験日程の詳細は以下の通りです。
| 出願期間 | 第Ⅰ回短答式試験 令和6年8月23日(金)~令和6年9月12日(木) 第Ⅱ回短答式試験 令和7年2月3日(月)~令和7年2月25日(日) ※論文式試験から受験の場合は第Ⅱ回短答式試験の出願期間に出願する必要があります |
|---|---|
| 短答式試験 | 第Ⅰ回短答式試験 令和6年12月8日(日) 第Ⅱ回短答式試験 令和7年5月25日(日) 企業法(60分)/管理会計論(60分)/監査論(60分)/財務会計論(120分) |
| 論文式試験 | 令和7年8月22日(金)~令和7年8月24日(日) 第1日目 監査論(午前120分)/租税法(午後120分) 第2日目 会計学<管理会計論>(午前120分)/会計学<財務会計論>(午後180分) 第3日目 企業法(午前120分)/選択科目(午後120分) ※選択科目は経営学、経済学、民法、統計学から1つを選んで受験 |
| 合格発表 | 第Ⅰ回短答式試験 令和7年1月17日(金) 第Ⅱ回短答式試験 令和7年6月20日(金) 論文式試験 令和7年11月21日(金) |
なお、試験科目の免除を受ける場合、あらかじめ免除申請を行なう必要があります。受験願書の提出前に申請しなければならないので、書面もしくはインターネットで必要な手続きを行ないましょう。
上記の日程が変更される可能性もあるので、あらかじめ確認しておきましょう。
公認会計士試験の難易度と勉強時間

公認会計士の試験情報を押さえたら、次は具体的にどのような戦略を立てて勉強すべきか検討しましょう。戦略立案に役立つ情報として、公認会計士試験の難易度や勉強時間についても解説します。
公認会計士は三大国家資格のひとつ
公認会計士は数ある国家資格の中でも特に医師・弁護士と並んで「三大国家資格」と呼ばれています。ここ数年の合格率は10%を切る値で推移しており、取得難易度の高い試験です。
| 年別 | 願書提出者 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 平成26年 | 10,870人 | 1,102人 | 10.1% |
| 平成27年 | 10,180人 | 1,051人 | 10.3% |
| 平成28年 | 10,256人 | 1,108人 | 10.8% |
| 平成29年 | 11,032人 | 1,231人 | 11.2% |
| 平成30年 | 11,742人 | 1,305人 | 11.1% |
| 令和元年 | 12,532人 | 1,337人 | 10.7% |
| 令和2年 | 13,231人 | 1,335人 | 10.1% |
| 令和3年 | 14,192人 | 1,360人 | 9.6% |
| 令和4年 | 18,789人 | 1,456人 | 7.7% |
| 令和5年 | 20,317人 | 1,544人 | 7.6% |
出典:公認会計士・監査審査会ウェブサイト
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/r5shiken/ronbungoukaku_r05/03.pdf
合格を手にするためには、しっかり戦略を立てて計画的・効率的に勉強することが大切です。
合格するために必要な勉強時間は?
勉強時間は人によって変動しますが、公認会計士試験に合格するための勉強時間は、一般的に3000時間が必要と言われています。
もっと多くの時間が必要などと様々な情報がありますが、合格までの平均年数が2~4年程度と言われていますので、単純計算で1日あたりの勉強時間を5時間とすると3650~7300時間が必要ということになります。
3000時間とは、2年で一発合格をするために必要な勉強時間の目安ということです。
いきなり最初から多くの時間を必要とするわけではなく、勉強スタート当初は、1日に2~3時間程度で、勉強が進むにつれて徐々に勉強時間が増えていくイメージです。
無理のない受験プランを立てる場合、全体の期間は1年半~2年程度に設定するのが一般的です。勉強時間は人によって変動しますし、一つの目安と考えて、学業や仕事との兼ね合いも踏まえながら、自分に合った戦略を検討しましょう。
公認会計士の試験勉強をする上でのポイント
公認会計士試験はとにかく出題範囲が広いので、やみくもに勉強しても合格することはできません。そこで、試験勉強における重要ポイントや科目別の勉強方法について解説します。
勉強する際のポイント
公認会計士試験に合格するためには、勉強時間を確保することはもちろん、ポイントを押さえて計画的・効率的に勉強することが大切です。特に重要な5つのポイントを紹介するので、ぜひ押さえておきましょう。
合格までの目標期間を決める
受験プランを立てるときは、いつ頃の合格を目指すのか、あらかじめ目標期間を決めることが大切です。例えば、1年での短期合格を目指す場合、1日あたり10時間以上の勉強時間が必要となります。
しかし、期間が倍の2年あれば、1日5時間ほどが必要な勉強時間となるため、学業や仕事をしながら目指せる人もいるでしょう。
苦手科目を作らない
短答式試験・論文式試験ともに1科目でも得点が40%未満になってしまうと、その時点で不合格になる可能性があります。そのため、公認会計士試験では、どの科目も偏りなく勉強して、苦手科目を作らないことが大切です。
反復学習を繰り返す
単に知識だけ暗記しても、公認会計士試験に合格することはできません。知識が定着するまで短期間での反復学習を繰り返して、その知識を自在に使いこなせるレベルまで高めましょう。
短答式試験の合格を目指す
公認会計士試験では、短答式試験の合格者のみ論文式試験を受験できるため、まずは基礎をしっかり身につけて、短答式試験に合格することが大切です。
短答式試験に合格すれば、2年間の免除期間が発生するので、その期間中は論文式試験の対策だけに注力できます。
財務会計論に重点を置く
公認会計士試験において、財務会計論は最も配点比率が高い科目です。合格者の勉強時間配分を見ても、財務会計論の計算と理論でそれぞれ約20%、全体の約40%を占めています。
他の科目はだいたい同じくらいの割合なので、財務会計論に重点を置いて勉強しなければ、合格できないといっても過言ではありません。
科目別の勉強方法/必修科目
必修科目の内容は、短答式試験・論文式試験どちらにも出題されます。そこで、おすすめの勉強方法を科目別にまとめました。
会計学(財務会計論/管理会計論)
財務会計論はテキストの例題や問題集を繰り返し解いて、解答パターンを押さえることが大切です。問題を見た瞬間に解答パターンが出てくるレベルを目指して、反復学習を徹底的に行ないましょう。
管理会計論もテキストの例題と問題集をメインに勉強して、計算・理論の基礎をしっかり身につける必要があります。完了したら、次は答案練習に取り組みましょう。論文式試験対策として、答案練習はスピード重視で問題を解くことが大切です。
監査論
監査論はテキストの内容をきちんと理解したうえで、問題を解くことが大切です。必要な知識を蓄えたら、次は実際の現場をイメージして監査基準における中心的理解を深めましょう。
企業法
企業法は短答式試験でも論文式試験でも、暗記だけである程度の点数を獲得できます。できるだけ多くの問題を解いて、しっかり知識を蓄えます。
租税法
租税法は論文式試験限定の科目ですが、論点を押さえて勉強すれば、点数も伸びやすいといわれています。覚えるべきことはある程度決まっているため、まずは暗記から始めるのがおすすめです。暗記で知識を蓄えたら、頻出論点をメインに答案練習を繰り返しましょう
科目別の勉強方法/選択科目
論文式試験では、4つの選択科目から1つ選んで問題を解くことになります。それぞれの特徴や勉強方法を踏まえながら、どの科目を選ぶか検討しましょう。
経営学
経営学は基礎問題メインで出題されるため、他の選択科目と比べて難易度は低めです。学習ボリュームが少ない分、勉強時間も少なくて済みます。実際、受験者の約80%は経営学を選択しているので、特別な理由がなければ経営学一択といえるでしょう。
経済学
経済学は出題範囲が広いうえ、数学の知識も必要なので、数学が苦手なら避けるべきです。経済学や数学が得意なら、選択する価値はあります。
民法
民法は条文自体が多いうえ、判例と併せて勉強しなければならないので、必然的に勉強時間も多くなりやすいといえます。大学で法律を専攻していたり、民法が得意だったりする方は選択しても良いでしょう。
統計学
統計学は覚えるべき内容こそ少ないですが、計算内容のレベルは非常に高いです。計算ミスにともなうリスクもあるので、計算が得意という方以外は選択しないほうが無難でしょう。
おすすめの勉強法と学習費用

公認会計士試験に向けたおすすめの勉強法、および学習にかかる費用の目安についても解説します。
独学
公認会計士の関連資格を取得している方や実務経験がある方、大学などで関連分野を専攻していた方なら、独学でも合格できる可能性はあります。独学はマイペースで勉強できること、学費を抑えやすいことがメリットです。
ただし、公認会計士試験は勉強を始めてから資格取得まで平均して2~4年、長ければ5年以上かかるほど難しいため、合格の可能性はあまり高くありません。
また、市販のテキストや問題集の数が少なく、質問できる相手もいないので、計画的・効率的な勉強が難しいというデメリットもあります。独学で合格を目指すなら、通信教材を併用することも検討しましょう。
なお、独学で勉強する場合、学費は約10万円~です。
通信教材
通信教材を利用すれば、独学のように自分のペースを維持しながら、カリキュラムに沿って計画的・効率的に勉強できます。通学する必要がない分、時間や交通費を節約できたり、周りに気を遣わずに済んだりすることもメリットです。
ただし、カリキュラムがあるといっても、基本的に一人で勉強しなければならないので、モチベーションを維持しづらいかもしれません。
実際、途中で挫折してしまったというケースも少なくないため、強い意志が必要不可欠です。
また、通信教材によっては質問を受け付けることもありますが、その場で質問できるわけではないので、レスポンスが悪いこともデメリットといえます。
なお、通信教材で勉強する場合、学費は約70万円~です。
資格スクール
資格スクールに通学すれば、カリキュラムに沿って計画的・効率的に勉強できるのはもちろん、勉強するという習慣を身につけられるので、合格に最も近い勉強法といえます。
わからないことがあれば講師にすぐ質問できる、一緒に合格を目指す勉強仲間ができるといったこともメリットです。
一方、資格スクールで勉強する場合、独学や通信教材より学費が高くなりやすいというデメリットもあります。選択するコースや期間によって異なる可能性もありますが、約70万円~の学費がかかると考えたほうが良いでしょう。
また、時間を作って通学しなければならないため、人によっては学業や仕事との両立が難しいケースも考えられます。
ただし、公認会計士という難関資格を取得するためには、学費や時間のデメリットを踏まえても、合格実績の高い資格スクールに通って勉強するのが現実的です。一発合格できれば、結果的に学費や時間を抑えられるので、検討する価値は大いにあります。
まとめ
公認会計士は人気の高い国家資格ですが、取得難易度も非常に高いので、きちんと戦略を立てて計画的・効率的に勉強する必要があります。合格者の多くは資格スクールで勉強していますが、特におすすめしたいのが「資格の大原」です。
資格の大原では、公認会計士試験のことを熟知しているプロの講師陣が多数在籍しています。効果的なカリキュラムに基づく徹底指導や、合格ノウハウが詰めこまれた新作オリジナル教材は、受講生の方々から高い支持を集めているため、初めて受験する方も心配無用です。
また、苦手科目克服に役立つ24時間利用可能なWeb講義や急な欠席をカバー、別な日に変更できる振替出席制度など、サポート制度も充実しているのでぜひ検討してみてください。