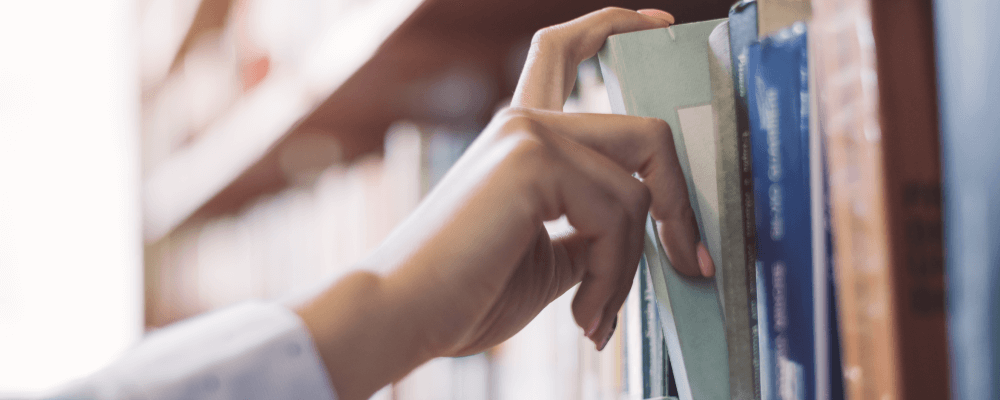1万種類を超える法的書類を顧客に代わって作成
行政書士
試験情報
法律系の資格取得を考えるときに、多くの人が最初に取得を検討するのがこの「行政書士」ではないでしょうか。「行政書士」は国家資格のひとつであり、法律関連の資格のなかでは比較的合格しやすい試験としてもとても人気のある資格です。ただ、知名度こそ高い「行政書士」ですが、その仕事内容や実際の働き方、活躍場所など実はあまり知られていません。ここでは実際の行政書士の仕事内容や、どんなフィールドで活躍できるのか、また仕事のやりがいなどについてご紹介します。
行政書士試験の情報は?合格するためのポイントも解説

行政書士の資格取得を目指すなら、まずは試験の日程や出題形式といった試験情報を知っておくことが大切です。試験情報を知っておくと、いつ勉強を始めたら良いのか、どういうポイントに注意して勉強を進めれば良いのかがわかってきます。
この記事では、「行政書士になりたいけど何から始めたら良いかわからない」という方のために、行政書士試験の情報と試験合格のためのポイントをまとめています。
ぜひ、この記事を読むところから、行政書士試験対策を始めましょう。
行政書士国家試験とは?
行政書士国家試験とは、行政書士法に基づいて年に1回実施される国家試験です。試験に合格し、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録されると、行政書士として業務を行なえるようになります。
行政書士試験の出題範囲は他の法律系資格よりも限られていますが、難解な法律を扱うため、試験の難易度が低いわけではありません。合格するには、試験の特徴を踏まえて学習を進める必要があります。
行政書士は独占業務を持つ国家資格で、書類作成・許認可申請の代理・相談業務(コンサルティング)などの業務を担います。取り扱う書類は幅広く、1万種以上にのぼるため、文書作成のプロフェッショナルといえる職業です。
行政書士試験の日程

行政書士を目指すなら、まずは試験の日程を確認しておきましょう。ここでは、試験の日程や受験資格などを具体的に解説します。
より詳しい試験情報は、一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページに掲載されています。試験の最新情報をチェックするためにも、目を通しておきましょう。
試験日程
行政書士国家試験は年に1回実施されます。試験情報の発表から合格証が送られてくるまでの例年の流れは、以下のとおりです。
7月上旬:試験情報の発表
行政書士試験研究センターのホームページで、試験の実施日や試験会場などが公表されます。住民票の所在地によらず、試験は全国各地のどの試験会場でも受けられるため、最寄りの試験会場を確認しておきましょう。
8月上旬~9月上旬:願書配布・受験申し込み受付
受験の申し込みは、インターネットまたは郵送で行ないます。添付書類が少ないため、願書作成にはそれほど時間がかかりませんが、できるだけ早く提出しましょう。
10月中旬~下旬:受験票の送付
11月第2日曜日:本試験
本試験は、午後1時から午後4時まで実施されます。
1月下旬:合格発表・合格通知書の送付
合格者は、行政書士試験研究センターのホームページ上で発表されます。そして、受験者全員に送付される合否通知書で、合否・配点・合格基準点・得点を確認できます。
2月中旬~下旬:合格証の送付
試験合格者に合格証が送付されます。
受験資格と手数料
行政書士国家試験に受験資格はないため、年齢・学歴・国籍に関係なく誰でも受験できます。
受験手数料は、例年10,400円です。インターネットで申し込む場合はクレジットカードまたはコンビニエンスストアで、郵送で申し込む場合は専用の振替払込用紙を使って郵便局窓口で支払います。
なお、郵便窓口で支払った際にもらえる振替払込受付証明書は、願書の郵送時に貼付しなければならないので、なくさないように注意してください。
試験会場
試験は現在の住まいや住民票の所在地に関係なく、任意の試験会場で受験できます。ただし、願書提出後に転勤・転居などがあっても、試験場は変更できないので注意が必要です。
試験会場に関する詳細は、7月上旬に行政書士試験研究センターのホームページで発表されるので、最新の情報をチェックするようにしましょう。
行政書士試験の内容と合格基準
ここでは、行政書士試験で出題される内容と試験の合格基準を解説します。
出題内容と形式
行政書士試験は、法令科目と基礎知識科目に分かれています。法令科目では行政法や民法などの法律に関する知識が問われ、基礎知識科目では一般知識、諸法令、情報通信・個人情報保護、文章理解が問われます。
なお、法令科目は、試験の実施日が属する年度の4月1日時点で施行されているものが出題範囲です。新たに施行されたり、改正されたりした法令については4月1日以降に確認すると良いでしょう。
問題の配点や出題形式は事前に公表されませんが、令和2年度試験の配点と出題形式は以下のようになっています。
| 試験科目 | 出題形式 | 出題数 | 配点 |
|---|---|---|---|
| 法令科目 | 5肢択一式 | 40問 | 160点 |
| 多肢選択式 | 3問 | 24点 | |
| 記述式 | 3問 | 60点 | |
| 基礎知識科目 | 5肢択一式 | 14問 | 56点 |
| 計 | 60問 | 300点 | |
配点を見てみると、法令科目が総得点300点中244点(約81%)を占めているため、法令科目の対策が試験合格の鍵を握るといえるでしょう。
合格基準
試験の合格基準は法令科目・基礎知識科目・試験全体でそれぞれ設けられており、そのすべてを満たすと試験合格になります。
法令科目・基礎知識科目・試験全体の得点のうち、一つでも基準を下回ると不合格になってしまうため、どの基準も最低限の得点を取れるように勉強時間の調整が必要です。
| 行政書士試験の合格基準 1~3すべてを満たすと合格できる | ||
|---|---|---|
| 1 | 法令科目 | 計244点のうち122点以上の得点 |
| 2 | 基礎知識科目 | 計56点のうち24点以上の得点 |
| 3 | 試験全体 | 計300点のうち180点以上の得点 |
行政書士試験は、他の受験生の得点に合否が左右されない絶対評価です。自分の実力アップだけに注力すれば良いので、周囲の点数や学習進度は気にせずに学習を進めましょう。
行政書士試験は難しい?合格率と難易度
ここでは、行政書士試験の難易度や合格率、合格のために必要な勉強時間を解説します。
行政書士試験の難易度
行政書士試験の合格率は例年10%前後で推移しています。
行政書士は難関資格ではありますが、法律系国家資格のなかでは入門的な存在であり、弁理士や司法書士などと比べると難しくはありません。
行政書士の試験は合格基準が明確で受験資格がないことなどから、しっかりと対策していけば、初めて法律を学ぶ方でも合格は十分可能でしょう。
ちなみに、行政書士以外の法律系国家資格の合格率は、弁護士39.2%、税理士20.3%、司法書士5.2%、弁理士9.7%などとなっています。
合格率だけを見ると、弁護士や税理士より行政書士のほうが、資格取得が難しいと感じるかもしれません。しかし、司法試験の受験者は行政書士試験と違い、法律を専門的に学んだ方ばかりです。
つまり、司法試験はより本気で資格取得を目指す方が多いからこそ、難関試験であっても合格率が高くなっているのです。
このように、合格率は必ずしも難易度に比例しているわけではありません。行政書士試験の合格率は低く、たしかに難しい試験ではありますが、あまり合格率を気にせず学習に取り組むと良いでしょう。
勉強はいつから始めたら良い?
勉強はいつから始めたら良い? 行政書士試験に合格するには、短くても半年、平均的には1年ほどの勉強期間が必要です。試験は11月に実施されるため、試験が実施される年の1月には勉強を始めておきましょう。
必要な勉強時間は、法律の学習経験の有無などにもよって変わり、法律を学んだことがない方の場合は1,000時間ほど必要とされています。1,000時間の勉強を1年間で行なう場合、平均して一日あたり約2.7時間の勉強時間が必要になると計算できます。
自分の生活スタイルで確保できる勉強時間を計算し、合格までに必要な期間を逆算してみてください。
行政書士試験に合格するための3つのポイント

ここからは試験合格を目指すにあたり、気を付けたい3つのポイントを解説します。
スケジュール管理を徹底する
行政書士試験対策には平均的に1年以上の勉強時間が必要で、場合によっては計1,000時間以上もの時間を確保しなければなりません。
とはいえ、勉強を長期間続けていると途中でモチベーションが下がり、挫折してしまうこともあるでしょう。
そこで重要となるのが、スケジュール管理です。スケジュール管理を徹底していれば、現在どの程度学習が進んでいるのか、あとどれだけ学習する必要があるのか把握できるため、モチベーションを維持しやすくなります。
特に、自分で学習進度を管理しなければならない独学の場合や、忙しくて勉強時間の確保が難しい社会人は、徹底したスケジュール管理が必要です。
試験の特徴を知って効率的に対策する
どのような試験でも、試験の特徴を知ることが合格への近道です。
行政書士試験は合格基準が明確で、合格点が他の受験生の影響を受けない絶対評価であることなどから、試験対策がしやすい特徴があります。
ここでは、法令科目と一般科目それぞれの学習のポイントをご紹介します。
法令科目は行政法と民法を重点的に
法令科目の計244点のうち、7割以上にあたる188点が行政法と民法から出題されています。行政法と民法で満点を取れれば、法令科目の合格基準である122点を超えるので、この2科目は重点的に対策しておきましょう。
それ以外の憲法や商法などは、基本的な問題を取りこぼさないように対策しておき、余裕があればより難解な問題にも挑戦してみてください。
基礎知識科目は6問以上を取れるように
基礎知識科目の配点は56点であり、法令科目の244点と比べてかなり低くなっています。しかし、基礎知識科目にも法令科目と同じく合格基準が設けられているため、配点が低いからといって対策しないわけにはいきません。
基礎知識科目では、一般知識、諸法令、情報通信・個人情報保護、文章理解などの幅広い知識が求められます。試験範囲が広く学習に時間がかかるものの、得点が上がりにくいためモチベーションが低下することがあります。
そのため、基礎知識科目では無理に高得点を目指さず、合格基準となる全56点中24点以上(14問中6問以上)を目標にして対策しましょう。
過去問をフル活用する
過去問は、知識の確認と仕上げのために必須の教材です。過去問を解くと試験の形式と傾向を知れるだけでなく、実際の試験での時間配分も学べます。
テキストでの学習と並行して過去問を解いたり、試験の数ヵ月前から知識の総復習として使用したり、過去問の使い方は人によってさまざまです。自分の学習スタイルに合ったタイミングで使えるように、過去問は早めに用意しておくことをおすすめします。
過去5~10年分の問題を繰り返し解き、解けなかった問題は必ず復習して知識の定着を図りましょう。
行政書士試験合格を目指すなら大原で!
行政書士専用講座がある大原なら、試験のポイントを押さえた効率的な学習で、短期間でも行政書士試験合格を目指せるでしょう。
ノウハウを活かした無駄のないカリキュラム
大原は数多くの試験合格者を輩出している実績があり、そのノウハウを活かした無駄のないカリキュラムで、受験生を試験合格に近づけます。
最新情報も網羅したオリジナルの教材
行政書士試験のように、法律に関する知識が問われる試験では、毎年の法改正に対応して試験対策をする必要があります。
大原のオリジナル教材は、法改正や試験の傾向を反映させるため毎年改訂されており、大原の教材だけで勉強が完結するようになっています。
試験の分析は経験豊富な講師陣が行なっているため、自分で試験対策するよりも、はるかに効率的に学習を進められるでしょう。
まとめ
行政書士試験は11月に実施され、多くの方は試験実施の1年ほど前から勉強を始めます。試験合格のためには、法律知識の有無や生活スタイルに合わせて、無理なく勉強を続けられるようにスケジュールを立てることが大切です。
試験の詳しい情報は、例年7月の上旬に行政書士試験研究センターに掲載されるので、忘れずにチェックするようにしましょう。
短期間で効率良く合格を目指すなら、行政書士専用講座のある大原の利用がおすすめです。数多くの合格者を輩出している大原なら、法律を学んだことがない方でも安心して学習を進められます。
大原に興味がある方は、まずは無料の資料請求や体験入学・説明会への参加から試してはいかがでしょうか。一発合格を目指す大原ならではのフォロー体制が整っているので、ぜひご活用ください。