
公認会計士の国家試験合格を目指そうと決めたものの、どのように勉強すればよいのかわからずに迷っているということはありませんか?
企業会計のスペシャリストである公認会計士は試験の難度が高く、難関といわれる国家資格の一つです。
この記事では、豊富な指導経験のある現役講師が、公認会計士試験の難度や合格率から効率的な勉強方法まで徹底解説します。ぜひ、受験勉強の参考にして、公認会計士試験の合格につなげてください。

髙橋尚彦(公認会計士)
公認会計士試験の受験指導歴は20年超です。担当科目は会計学(管理会計論)を担当しています。
大手監査法人での実務経験も活かして、講義では製造業やサービス業でのコスト管理の実例を用いながら、受験生が現場の状況をイメージしやすいように説明しています。
演習解説では受験生の皆さんの得点力向上のために、問題文から重要なポイントを見極める技術、効果的に問題を解くためのアプローチ、そして明確で整理された下書きの作成方法を伝えることを重視しています。
国家資格のなかでも難しいとされる公認会計士は、医師や弁護士と並ぶ「3大国家資格」といわれることもあり、試験の合格率は低くなっています。
過去5年間の合格率
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第Ⅰ回短答式試験 | 15.7% | 21.6% | 12.1% | 10.4% | 10.8% |
| 第Ⅱ回短答式試験 | 12.9% | 7.9% | 8.8% | 9.5% | |
| 論文式試験 | 35.9% | 34.1% | 35.8% | 36.8% | 36.8% |
| 合格者/出願者 | 10.1% | 9.6% | 7.7% | 7.6% | 7.4% |
短答式については、8~15%程度、論文式については、35%前後となっており、論文式の方が、合格率が高いですが、短答式を突破しないと受験できないので、難度の高さが伺えます。また、短答式試験は年に2回(12月および5月)、論文式試験は年1回(8月)実施されます。論文式試験を受けるチャンスは年に1回しかないため、モチベーションの管理が重要になってきます。
※2020年公認会計士試験(第II回短答式試験及び論文式試験)が新型コロナウイルス感染症拡大状況等を踏まえて、大幅に日程を延期して行うこととしたことに伴い、2021年公認会計士試験については、短答式試験を1回のみの実施。

司法試験等とは異なり、短答式試験(マークシート式)よりも論文式試験(記述式)のほうが、合格率は高くなっています。また、論文式試験とは言っても、公認会計士試験の場合、その試験問題のおよそ半分は会計や税務に関する計算問題です。公認会計士試験は狭き門ではありますが、長い文章を書く自信がないという理由で尻込みする必要はありません。
前述のとおり、合格率の低さから難度が高いといわれる公認会計士試験ですが、難度が高い理由は他にも2つあります。
公認会計士試験は、財務会計論、管理会計論、監査論、企業法(会社法/商法/金融商品取引法)、租税法(法人税/所得税/消費税)のほか、選択1科目(経営学・経済学・民法・統計学より選択)で構成されています。
科目数が多いため勉強する範囲は当然広くなりますし、どの科目も専門性や難度が高いため、合格するには多くの勉強時間が必要です。
しかも、短答式試験はマークシート式、論文式試験は記述式と、試験方式が異なるため、それぞれに応じた対策が必要となります。
公認会計士試験と比較されることも多い税理士試験の場合、科目合格制のため1科目ずつ受験できるほか、合格した科目については恒久的に合格が認められます。
しかし、公認会計士試験はすべての科目を一度に受験しなければいけません。短答式合格、および論文式の科目合格というものはありますが、いずれも試験免除期間は2年間のみです。
つまり、科目合格制の税理士試験とは異なり、試験免除が認められている2年以内に論文式試験で最終合格できなければ、もう一度短答式からスタートすることになります。
また、部分的に科目合格が認められているとはいえ、科目合格の基準はかなり厳しく設定されており、免除期間にもあまり余裕はないため、基本的には一発合格を見据えて勉強したほうがよいでしょう。
このような事情からも、勉強時間の確保が難しい社会人にとっては、公認会計士試験は特に難度が高い国家試験といえるのです。

多くの科目を同時に勉強しなければならないため、受験生は、各科目の内容の難しさだけではなく複数科目を並行して勉強するための効率的なスケジュールの策定にも苦労することになります。公認会計士試験が、予備校に通わずに独学で合格するのは難しいといわれるのはそのためです。
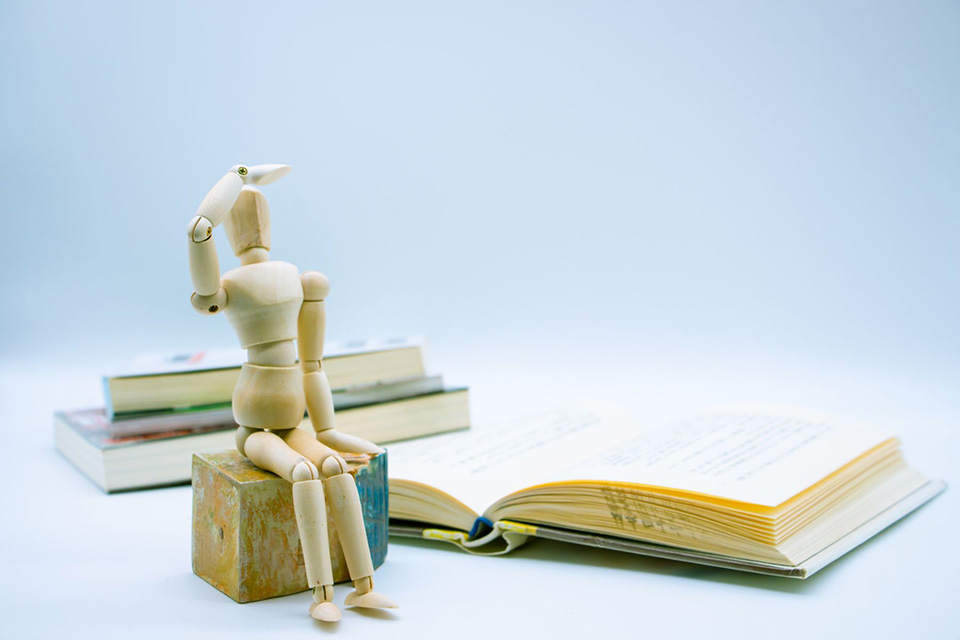
公認会計士試験の難度は税理士試験や簿記1級と比較されることが多いのですが、ここではそれぞれの試験を比較したうえで、求められる能力や試験の受けやすさについて解説します。
税理士試験と公認会計士試験を比較する場合、おおよそのイメージとして税理士試験には「暗記力」、公認会計士試験には「思考力」が求められると考えればよいでしょう。
もちろん、単純に比較できるものではないので、あくまでもイメージですが、試験科目の名称からもある程度推察できます。
例えば、税理士試験では「○○税法」というように、法律によって決められていることを学ぶため、数字や計算方法など丸暗記しなければならない要素が多くなります。
一方、公認会計士試験では「○○学」「△△論」のように考え方を学ぶ科目が多いため、思考力や理解力が必要とされやすいのです。
なお、試験制度の違いから、1科目ずつ受験できる税理士試験では、1回の受験における勉強量を抑えられる一方、公認会計士試験はほぼ一発勝負のため、受験に専念できる環境のある人が受験者に多い傾向にあるといえます。
この傾向は年代別の受験者数にも表れており、公認会計士試験では20代前半が最も多く全体で4割を超えているのに対し、税理士試験で最も多いのは40代以上で4割弱となっています。
また、公認会計士試験には受験資格が設定されていないことも、勉強時間を確保しやすい学生のうちに資格取得を目指す人が多い要因といえるでしょう。
簿記1級の試験範囲は、公認会計士試験の試験範囲に含まれています。ですので、公認会計士試験と簿記1級試験を比較した場合、公認会計士試験のほうが勉強量は多く、難度は高いです。
公認会計士は簿記の延長線上にあるような資格であるため、先に簿記3級や2級を取得しておくことで、公認会計士試験の勉強を進めるうえで役立ちます。
公認会計士試験の勉強をするうえでも基礎がわかっていることはプラスに働くので、簿記3級・簿記2級を取得してから公認会計士試験の勉強を始めるのもよいでしょう。

公認会計士試験を受けるかどうか迷っている方は、試しに簿記検定の勉強をしてみてはいかがでしょう。簿記の勉強が肌に合う方は、公認会計士試験の勉強にも向いています。公認会計士試験を受けるかどうか迷っていない方は、わざわざ簿記検定の勉強から始める必要はありません。すぐにでも公認会計士試験の勉強を始めましょう。
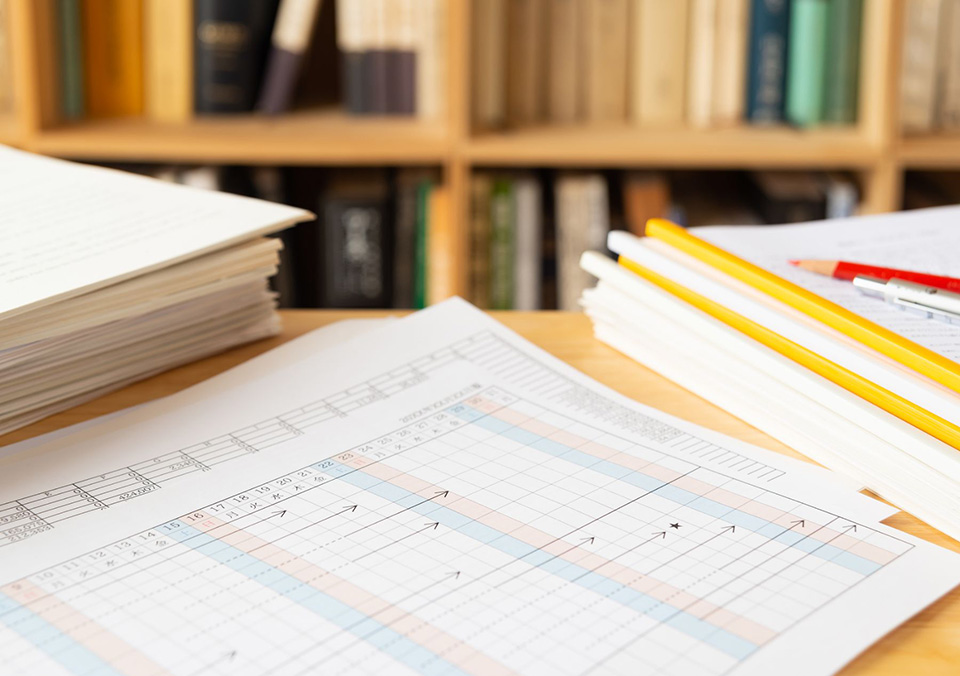
ここからは公認会計士試験に合格するには、どのような方法で勉強を進めていけばよいのか、具体的な勉強方法とポイントを紹介します。
まず考えるべきは勉強時間の確保です。自分は週に何時間勉強できるのか、生活リズムを変えることで勉強にあてられる時間をもっと増やせないか、色々と工夫してみましょう。
十分な勉強時間が確保できなければ、どんなに効率的な勉強を実行したとしても、公認会計士試験に合格することはできません。
来年の合格を目指すべきなのか、それとも再来年の合格を目指すべきなのか、勉強に費やせる時間によっては目標年度自体を変える必要があります。
勉強時間が確保できたら、あとは集中して勉強するだけです。基本的には予備校等のカリキュラムに沿って勉強を進めることになりますが、ここで重要なのは安易にカリキュラムから逸脱しないこと。
復習が多少遅れていたとしても、次の講義を受けるのを遅らせたりしないことが重要です。公認会計士試験はとにかく試験範囲が広いので、すべてを完璧にすることは不可能です。
多少不安な論点があったとしても、仕方がないと割り切りながら進みましょう。先の論点を習うことで前の論点の理解が深まるといったことも珍しくありません。
予備校のカリキュラムは一見するとそんなにきついものではありません。短期合格を目指すコースでも、講義は基本的には1日1コマです。これは、公認会計士試験の受験勉強では講義よりも復習のほうが大切であることを意味しています。
会計や税務の計算問題が多い公認会計士試験では、講義で理解した内容について大量の演習問題をこなさなければなりません。会計処理の仕組みをどれだけ深く理解していても、それを早く正確に行うためには、慣れるための反復演習が不可欠なのです。
公認会計士試験に合格するまでの総学習時間の目安としては、おおよそ3,000時間程度が必要といわれていますが、受験生の科目に呈する得意不得意などによっても変わってきます。
なお、スクールを活用することを前提とするならば、概ねコース内で学習する時間と復習時間の合計となり、個々人の必要な復習時間数によって大きく変わります。
ただし、この学習時間というのは本人の集中力や科目に対する適性によって変動する部分も大きいため、これだけの時間を勉強にあてれば公認会計士試験に必ず合格できるというものではありません。あくまでも目安として考えておきましょう。
科目別の勉強法を紹介します。

公認会計士試験に合格するためには性質の異なる多くの科目を並行して勉強する必要があります。そのため、各科目の特徴を理解して正しい勉強計画を立てることが重要です。正しい計画を立てないと、いつの間にか苦手科目ができてしまうといった事態にもなりかねません。専門家のアドバイスを積極的に受けてください。
公認会計士は難度の高い国家資格ですが、公認会計士試験そのものは年齢や性別、学歴に関係なく受けられるため、20代前半で受験する方が最も多いのが特徴です。
しかし、出題範囲が広いことや、1回の試験で全科目を受験しなければならないことから独学で合格を目指すのは難しく、効率的に合格を目指すには資格スクールや予備校に通うことをおすすめします。
資格の大原で開講している公認会計士講座では、現行の試験制度になった2006年~2024年までに9,813名(社会人講座8,958名、専門課程855名)の合格者を輩出しています。
総合成績上位者も多数輩出しており、2022年は全国総合成績1位、2位、4位、9位が大原生でした。
また、2014年と2017年には全国総合成績の1位・2位・3位を大原生が独占したほか、2013年には上位10名中7名が大原生、2015年は上位10名中6名が大原生という実績もあります。
資格の大原の公認会計士講座では、一発合格主義をモットーにしています。講義で使用するのは講師自身が作成監修したオリジナル教材で、試験内容の分析を反映して毎年新作を提供しています。
一般的に、スクールの規模が大きくなると常勤講師の割合が低くなるため、情報を統一してスクール独自の教材を開発するのは難しくなります。
一方、スクールの規模が小さくなると受験生に関する情報が十分に得られないため、一般的な受験生が効率的に合格レベルに到達する教材を開発するのは難しいでしょう。
このようななか、資格の大原はスクールの規模が大きいにも関わらず常勤講師の割合が高く、全国の常勤講師がさまざまな情報を共有しています。これにより法改正や制度改正にも正確かつ迅速な対応ができるため、教材の開発力も高くなるのです。
理想のカリキュラムとオリジナル教材、プロ講師による講義など、公認会計士試験合格に必要な環境をすべて用意していますので、安心して学習に集中できます。
資格の大原が開講している公認会計士講座では、映像視聴学習のためだけに収録された専用講義もあり、24時間いつでも利用できるほかアプリにダウンロードすることも可能です。
オリジナル教材を使用した講義は北海道から沖縄まで全国どこでも同じ授業を実施しているため、住んでいる地域やスクールの立地に関係なくプロ講師による質の高い授業が受けられるほか、大原各校での振替出席制度を利用できます。
また、資格の大原では全国規模で受講生をバックアップする、就職サポートプログラムを用意しています。
公認会計士は「3大国家資格」の一つで、合格率7~10%程度という高難度の試験に合格しなければ取得できない国家資格です。
年齢や学歴などの受験資格の制限はなく、勉強時間を確保しやすい20代前半の受験者が最も多いのが特徴でもあります。
公認会計士試験は出題範囲が広いため独学で勉強するのは難しく、効率的に勉強するなら資格スクールや予備校に通うのがおすすめです。
資格の大原では公認会計士試験の一発合格をモットーに、教室通学・映像通学、通信講座を開講しています。各講座のパンフレットを無料でお届けしますので、資料請求をご希望の方は下記フォームよりお申し込みください。
また、講座説明会や学習法セミナーなどのイベントを定期的に開催していますので、興味のある方はぜひご参加ください。

大原の講師が徹底解説!
受講中の方へ
合格者の方へ
資格の講座以外の学習スタイル
大原学園グループでは、この他にも資格を取得できる学習スタイルをご用意しています。