
消防本部の職員として勤務する消防士(消防官)は地方公務員であり、各自治体に消防隊員として所属します。
消防士(消防官)になるには、採用試験に合格し、災害現場での職務を遂行するための訓練を行なわなければなりません。
消防士(消防官)という職業は特殊性が高く、一般的な公務員試験とは異なる受験資格が設けられており、事前に受験資格を確認しておく必要があります。
この記事では、消防士(消防官)になるまでの工程や、採用試験で試される内容を具体的に解説しますので、ぜひ消防士(消防官)を目指す際の参考にしてください。
(2024年8月 更新)

・氏名:宮澤太輔
・所属:資格の大原・公務員講座(東京水道橋校)
・常に全力をモットーに受講生指導にあたっています。また、一人ひとりに合わせて、面接や相談に何度でも対応しています!
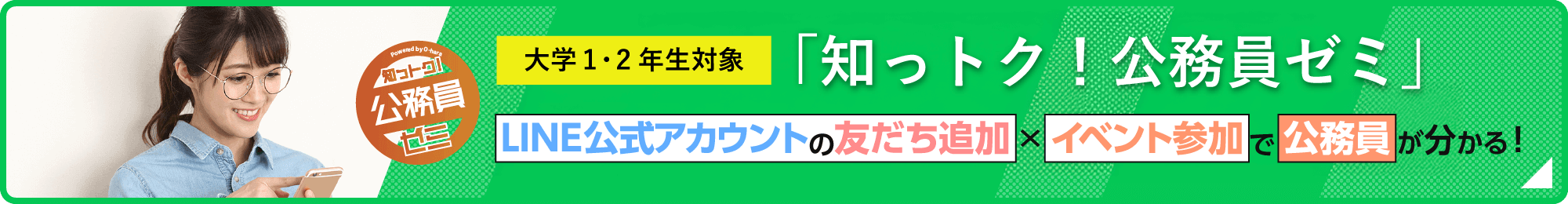
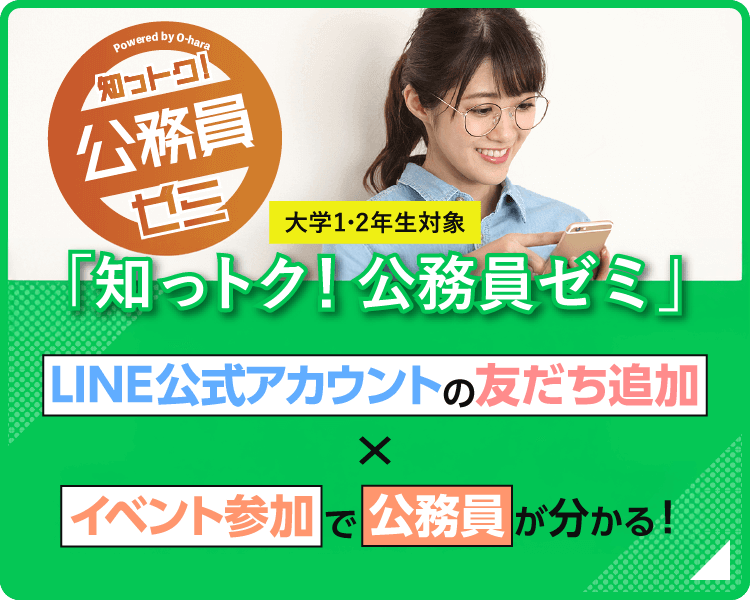
通常、一般の公務員は採用試験に合格すれば就職先での業務が始まりますが、消防士(消防官)の場合は消防学校に入学します。
ここでは、採用試験および消防学校入学後の概要を解説しますので、順に確認していきましょう。
地方公務員である消防士(消防官)になるには、まず各自治体で行なわれる消防士(消防官)の採用試験に合格しなければなりません。
試験の形式は、筆記がメインの第1次試験と、面接などを行なう第2次試験に分かれており、両試験の結果を総合的に判断し、合否が決められます。
受験資格や試験内容、難易度などは自治体によって異なりますが、受験資格を満たしていればどの試験においても受験可能です。
試験日程も自治体によって異なるため、就職を考えている自治体の日程を確認しておくとよいでしょう。
また、試験の日程が異なる自治体に関しては併願が可能です。試験日程を事前に確認し、リスク回避として併願するのも対策の一つです。
消防士(消防官)の採用試験に合格したら、消防学校に入学します。消防学校は全寮制になっており、訓練や学習といった初任教育が実施され、半年間で修了するのが一般的です。
消防学校で生活している間は、学校の制度やカリキュラムに則り、座学や実習を行ないます。公務員として知っておくべき法律に関する知識や、火災が起こるメカニズム、実習においては消火訓練や心肺蘇生など、本番さながらの学びとなるでしょう。
消防士(消防官)には夜間当直があることから、消防学校でも当直のシフトを組み込むなど、消防士(消防官)ならではの学校生活が特徴です。
なお、消防学校では、在学中でも自治体から給料や手当などの支給があります。一般的な学生とは異なり、早い段階で消防士(消防官)としての自覚が培われ、職務に対する責任感が生まれるでしょう。

消防士(消防官)になるためには、教養(筆記試験・論作文試験)とコミュニケーション能力(人物試験)が第一の関門となります。それぞれ、計画を立てて対策していくことがベストですね。
また、無事に採用が決まっても、その先が「スタート」です!消防士(消防官)の仕事内容の理解、自分自身が消防士(消防官)として何をやっていきたいかを少しずつ明確にしていくのも大切ですね!
消防官採用試験は、一次試験と二次試験が行なわれ、一次試験に合格した者だけが二次試験に進める仕組みです。
ここでは、試験の概要を具体的に解説しますので、受験勉強の参考にしてください。なお最新情報については、各自治体の公式サイトで確認しましょう。
一次試験では、教養や適性検査、論作文など、おもに筆記の試験が行なわれます。
まずは、教養試験の一つである「一般知能科目」について解説しましょう。一般知能科目は、資料の読み取り問題や数的パズルといった「数的処理」、古文の読解力や現代文などによる「文章理解」の問題となります。
数的処理の問題は、出題数が多い傾向にあるため、過去問による繰り返し練習や解法パターンの分析、時間配分などの対策が重要です。
文章理解の問題は、古文、英文、現代文から構成されています。日頃から小説や新聞を読むなど、文章に触れる機会を増やすことが有効な対策といえるでしょう。
次に「一般知識科目」について解説します。一般知識科目では、社会科学、人文科学、自然科学、時事などを中心とした構成です。
経済や法律、政治などで構成された「社会科学」は、出題数が多い分野のため、網羅的な対策と並行し、頻出するテーマに焦点を当てた学習が効果的といえるでしょう。
「人文科学」では、日本史をはじめ、世界史、地理、文学芸術など、文系科目を中心とした構成になっています。出題数は少ない傾向ですが、頻出問題を分析し、効率な勉強法を心がけましょう。
理系科目中心で構成された「自然科学」は、数学や化学、物理、生物、地学などについて出題されます。基礎を丁寧に学習し、苦手科目を克服するのが有効な対策です。
「論作文試験」は、毎年同じテーマが出題されるわけではありません。まずは文章の基礎を学び、過去の出題テーマや予想テーマを参考に、文章を書いてみましょう。文章力の向上には、第三者に添削してもらったり、評価を仰いだりするのが効果的です。
二次試験では、個別に面接したり、体力検査を行なったりと、人物試験を中心に進められます。
二次試験においても配点の割合は高く設けられているため、筆記試験と同様に対策する必要があるでしょう。
体力検査の基準となっているのは、文部科学省が発表している「新体力テスト実施要網(20歳~64歳対象)」です。
基本的には自治体ごとに合格基準が設けられ、基準に達した者が採用対象となります。試験内容は、握力や肺活量、腕立て伏せ、懸垂など、日常生活でも鍛えるのが可能な項目が多い傾向です。
ほかにも、長座体前屈や上体起こし、反復横跳び、シャトルランなどが行なわれます。消防士(消防官)が実際に現場で行動するような運動量までは試されませんが、最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、日頃から運動する習慣を設けるとよいでしょう。
個別の面接(口述試験)では、自己PRや消防士(消防官)を目指した志望動機、行ないたい仕事やその理由などが質問される傾向です。
質問の内容に対し、的確な回答ができるよう、さまざまな質問を想定したシミュレーションを行なう必要があります。
また、時事的な質問を投げかけられた場合でも瞬時に回答できるよう、日頃からニュースや新聞に目を通し、自身の考えや意見を整理しておくのも有効です。

筆記対策は、「数的処理」対策が最優先事項です。「判断推理」「空間把握・図形」「数的推理・資料解釈」と学習する内容は多いです。まずは、自分に合った内容を優先して学習することがいいですね。
また、論作文試験は東京消防庁以外だと、「自己PR」系の内容が多いですが、東京消防庁は「行政課題」系も出題される可能性があります。面接練習も含めて、資格の大原では、その部分もしっかりフォローしていきます!

消防士(消防官)の採用試験では、一般的な公務員の受験資格とは異なる基準が設けられており、自治体によっても異なります。
募集人数や受験者数により、倍率にも大幅な違いがあるため、希望数する就職先の募集要項を確認する必要があるでしょう。
ここでは、おもに東京都の受験資格を参考に、年齢制限や試験の倍率について解説します。
消防士(消防官)の試験には年齢制限がありますが、自治体によって異なるため、事前に就職を考えている自治体の受験資格を調べておくとよいでしょう。
自治体の多くは、試験の種類ごとに18歳~30歳くらいに設定されています。
例えば、令和6年度の東京消防庁試験の受験資格は下記となります。
なお、上記のように年齢制限が設けられているものの、新卒でなければ受験できないというわけではありません。受験資格さえ満たしていれば、経歴を問わず誰でも試験を受けられます。新卒であっても中途採用であっても、状況が不利になることはありません。
また、身長や体重などにも受験資格が設けられているところもあり、男女ともに基準を満たさなければ、消防士(消防官)の採用試験は受けられません。
なお、身体的な受験資格において「おおむね」や「およそ」と表記されている項目に関しては、大きな差でなければ受験できる可能性があります。各自治体の基準を確認し、大幅な数値のズレがないか調べてみましょう。
令和5年度の東京消防庁試験結果によれば、消防士(消防官)を受験した総応募者数は7,945人、最終合格者数が1,276人という結果が出ています。
実際に受験した人数をもとに計算すると、倍率は5.0倍ですが、年度や試験区分によって変動が大きいため、倍率に関係なく合格できるよう、学習に励むことが重要です。
教養試験に関しては、試験内容の範囲が広く、基準点に達しなければ論文の採点が行なわれません。自身の苦手分野が何なのかを分析し、確実に得点できる対策が重要といえるでしょう。
なお、募集人数は全国共通ではありません。各自治体によって異なるので、就職希望先の募集人数を確認しましょう。

一つ一つの対策を計画的に行ない、「諦めない」で試験当日まで「やり続ける」ことが最も大切です。倍率は関係なくなります。
自治体によっては、募集人数や募集の有無は、年によって異なります。ご自身が受験予定に入れている自治体HPは常にチェックするルーティンをつけておきましょう!
さまざまな災害現場に立ち向かわなければならない消防士(消防官)には、過酷な状況下において、職務を遂行するためのスキルが求められます。
ここでは、消防士(消防官)に求められる3つのスキルについて解説しますので、受験前に理解しておきましょう。
危険をともなう災害現場では、常にチームで行動し、連携を取りながら迅速に救助活動を行ないます。
1人でも多くの人を救助するためには、状況を踏まえた救助計画やチームの方針、出される指示に従い、的確な判断による行動が不可欠です。
過酷な災害現場では、1人の力で救助するのが困難な状況でも、チーム全体の力を合わせることで救助可能な場面が多く見受けられます。
的確な救助計画を立てるためには、報告や相談を怠らず、迅速に指示を理解するコミュニケーション能力が必要です。
消防学校での集団生活には、常にチームで行動するための考えを養う意図が含まれています。常にチームワークを意識し、集団での行動を尊重できる消防士(消防官)を目指せば、現場での活躍が期待されるでしょう。
人命救助を行ないたいという気持ちは重要ですが、気持ちに体力がともなっていなければ、現場での救助活動は非常に厳しいのが現実です。
足場の悪い災害現場では、酸素ボンベや防火服を装備し、要救助者を抱えながら動き回る体力が求められます。
また、火災現場では、火災の熱に耐えながら消火活動や救助活動を行なわなければなりません。そのような状況でも冷静な判断で行動しなければ、非効率な作業につながり、必要以上の体力を消耗するでしょう。
消防士(消防官)は、過酷な現場でも対応できるよう、日頃からさまざまなトレーニングを行なっており、全身を鍛え上げています。
あらゆる状況を想定し、がれきの撤去やロープを渡る訓練など、体力だけではなく、救助活動に活かせる技術力を高めるのも任務の一つといえるでしょう。
どれだけ危険な状況を目の当たりにしても、冷静な判断で行動できる精神力を持ち合わせていなければ、救助活動に支障をきたす可能性があります。
事故や災害、火災など、消防士(消防官)が向かう現場はさまざまな状況が想定され、時として目を覆ってしまいたくなるような、厳しい状況が待っているかもしれません。
消防士(消防官)になるには、恐怖や緊張、責任といった感情が湧いても、冷静な判断に切り替えられる精神力が必要です。

消防士(消防官)は常に命と隣り合わせの仕事です。一つ一つの行動や思考が、ご自身や要救助者の生命や財産を守ることにつながります。今までのご自身の歴史や公務員就活を通して、消防士(消防官)としての資質を磨いていきましょう!

消防士(消防官)になるには、高い倍率の採用試験に合格しなければなりません。試験までの時間配分を考慮した場合、効率的かつ効果的な勉強法で試験合格を目指すのがよいでしょう。
ここでは、大原が消防士(消防官)の試験に強い理由や、大原の講座で行なっている取り組みなどを解説しますので、受験勉強を開始する際の参考にしてください。
大原がこれまで積み上げてきた信頼は、多くの合格者を輩出したという実績にあると考えています。
公務員の第1次筆記試験において、のべ合格者数は20,345名に上り、消防士(消防官)や警察官、自衛官などの職種別では13,274名という実績を誇ります。
大原が消防士(消防官)の試験に強い理由は、初心者でも安心して学べるよう、基礎から積み上げるカリキュラムがあるからです。
消防士(消防官)を目指すうえで、面接試験の突破は必須です。感覚ではなく、実力としてコミュニケーション能力を身に付けられる対策は、大原ならではの強みといえるでしょう。
大原の「集中資格コース(全日)警察官・消防官」では、担任による定期的な面談を行なっており、一人ひとりがどれだけ理解度を上げているかの把握に努めています。
習熟度の把握により、状況に合わせた的確なアドバイスや、受験計画に合わせた受験先の選択など、試験合格にフォーカスしたサポートが可能です。
また、個別で質問できる体制が整っていることで、疑問点などを早い段階で解消でき、安心して試験合格に向けた学習が行なえます。
独学では習得が難しい面接対策では、段階ごとのカリキュラムが組まれており、要点を一つひとつ丁寧に習得できる充実した内容です。
消防士(消防官)の試験では「上級(Ⅰ類)」「中級(Ⅱ類)」「初級(Ⅲ類)」と、年齢によって区分が設けられています。
大卒程度の難易度とされている上級(Ⅰ類)試験は、年齢制限の設定が比較的高めで、受験先の選択肢が多いのが特徴です。
受験資格を満たしていれば、新卒の方でも中途の方でも、上級試験に合格する可能性は十分にあるでしょう。
大原の学習環境なら、基礎から応用まで身に付けられる問題演習が実施され、着実なレベルアップが見込めます。
使用する教材や問題集は上級レベルの内容までカバーされており、大卒程度の試験にも挑戦可能です。
教材や問題集はすべて学費に含まれていますので、追加費用の心配もありません。安心して試験勉強に注力しましょう。
場合によっては非効率な学習方法になってしまうというデメリットも持ち合わせていますが、環境に左右されない学習が独学のメリットといえます。
時間や金銭的な心配があるなど、独学で試験合格を目指したい方には「パススル 公務員(教養)」がおすすめです。
パススル公務員はスマホ一つで学習が進められるのが大きな特徴です。1チャプター約10分の講義なのでスキマ時間の学習も可能となります。
また問題集やミニテストなどのアウトプットもスマホでできる画期的な学習スタイルです。 効率よく学習したい方にオススメの講座です。

予備校に通う最大のメリットは、「最短距離」で「効率よく」対策できるところです。資格の大原では、「公務員試験を科学」し、常に最新の情報をアップデートし続けています。「消防士(消防官)」になってみようかなと思ったら、まずは「資格の大原」に相談してください!
地方公務員である消防士(消防官)になるには、倍率の高い採用試験を突破しなければなりません。
自ら勉強のスケジュールを立てたり、テキストを用意したりする独学による勉強法では、その方法が正しいのかわからないため、非効率なだけでなく、効果も得られない可能性が高まります。
これから大学に通うことを考えた場合、受験できるのは最低でも4年後です。年齢制限があることを考慮した場合、早めに受験する方法を選択するべきではないでしょうか。
効率よく試験合格を目指すなら、目指している試験に適した勉強法をサポートしてくれるスクールの受講が有効です。
大原では、学習法に関するセミナーや講座説明会を開催しています。定期的に行なっておりますので、お気軽にご参加ください。

大原の講師が徹底解説!
資格の講座以外の学習スタイル
大原学園グループでは、この他にも資格を取得できる学習スタイルをご用意しています。