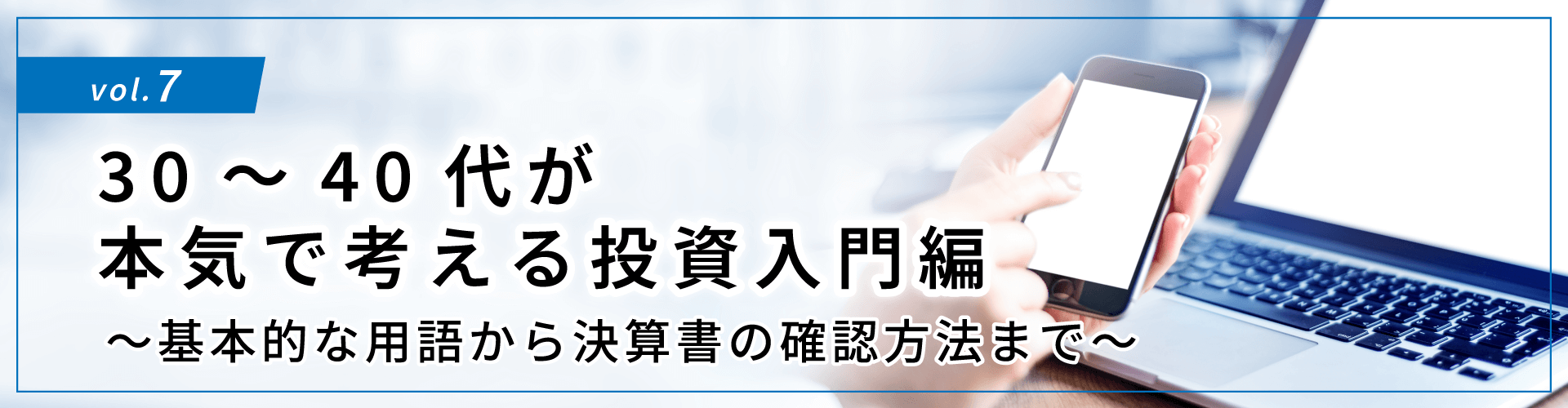
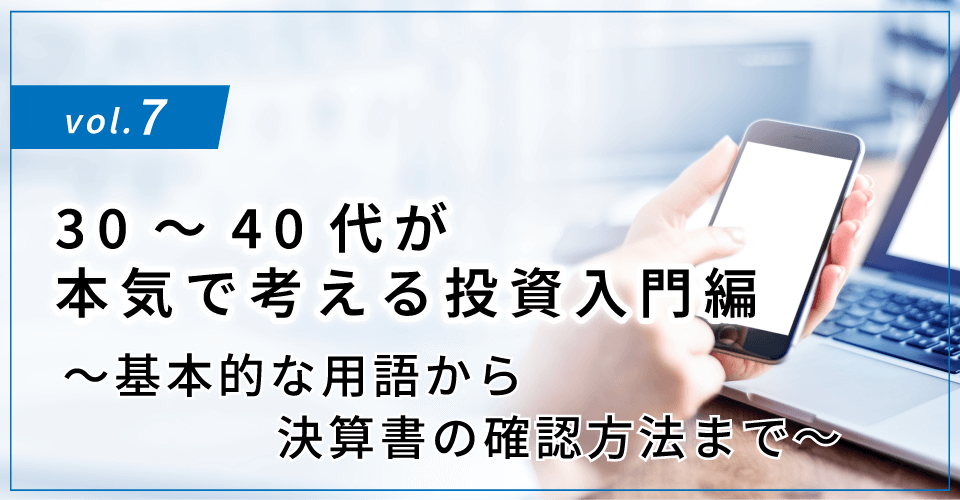
資格の大原による、お役立ち情報をお届けするコラムシリーズです。
(公開:2024.11.14)

2024年1月、日本の資産形成の新時代を告げる「新NISA」がスタートしました。従来の一般NISAとつみたてNISAを統合し、より柔軟で長期的な投資を可能にする制度へと生まれ変わったのです。また、近年注目を集める「FIRE」など、日本ではさらに投資への関心が高まっています。本記事では、30~40代が本気で投資を始めるために知っておきたい日本の資産運用環境や、基本的な用語、決算書の確認方法について解説します。

日本経済は大きな転換点を迎えています。日銀のマイナス金利政策解除により、約10年続いた異次元緩和からの出口戦略が始動。この変化は、私たちの資産形成戦略にも新たな視点をもたらしています。
特に40代以降の社会人にとって、この環境変化は重要な意味を持ちます。預金金利の上昇が期待される一方、住宅ローン金利も上昇傾向にあり、家計のキャッシュフロー管理がこれまで以上に重要になっています。
さらに、インフレ継続による実質的な資産価値の目減りも無視できません。単に預金に頼るだけでは、将来に向けた十分な資産形成は困難です。このような状況下では、分散投資によるリスク管理がより重要性を増しています。
投資環境を見ると、グローバル株式市場は変動性を増しているものの、AI関連企業の躍進や日本企業の構造改革進展など、中長期的な投資機会も広がっています。債券市場でも、金利上昇に伴い、新たな投資機会が生まれつつあります。
このような転換期だからこそ、投資の基本に立ち返ることが重要です。長期・分散・積立の原則を守りながら、新NISA制度などを活用した計画的な資産形成が、将来の経済的自由度を高める鍵となります。

30~40代は、資産形成の重要な時期です。住宅ローンや教育費など大きな支出が控える一方で、収入も安定し始める世代。この時期だからこそ、リスクと向き合いながら賢明な投資戦略を立てることが重要です。リスクに関して、この年代は「適度なリスクテイク」が可能です。まだ現役期間が20年以上あり、市場の変動に対する時間的な余裕があるためです。例えば、ポートフォリオの60~70%を株式型投資信託に、残りを債券型やREITに配分するなど、やや積極的な運用も検討できます。
一方で、40代以降の資産運用では、リターンを追求しながらもリスク管理が特に重要です。老後資金の形成期間が20代・30代と比べて短いため、大きな損失は避けなければなりません。
資産運用におけるリスクは、完全に排除することはできませんが、適切な管理は可能です。その核となるのが「分散投資」です。地域、資産クラス、通貨など、様々な観点での分散が重要です。例えば、国内株式だけでなく、先進国・新興国の株式、債券、REITなどを組み合わせることで、リスクを抑えながら安定的なリターンを目指すことができます。
また、「配当戦略」も資産運用で重要な要素です。高配当株式や配当性向の安定した企業への投資は、インカムゲインという形で定期的な収入をもたらします。特に、配当貴族と呼ばれる長期にわたり増配を続けている企業や、高配当のREITは、安定的な収入源として注目に値します。
ただし、高配当だけを追求するのは危険です。配当利回りが極端に高い場合、企業の財務状態に問題がある可能性があります。配当の持続可能性を判断するために、配当性向や財務健全性のチェックが欠かせません。
理想的なポートフォリオは、成長性のある企業への投資と安定した配当収入のバランスを取ることです。市場環境や自身のライフステージに応じて、このバランスを適切に調整していくことが、長期的な資産形成の成功につながります。

「人生100年時代」と言われる今日、老後までの資産形成は若いうちから意識すべき重要な課題です。特にNISA(少額投資非課税制度)とiDeCo(個人型確定拠出年金)は、早期に始めることで大きな効果を得られる制度です。
最大の理由は「複利効果」の威力です。例えば、20歳から月2万円を年利5%で運用した場合、60歳時点で約2,400万円になります。一方、35歳からスタートすると約1,000万円にとどまります。15年の開始時期の違いが、最終的な資産額を2倍以上も変えてしまうのです。
また、若いうちは投資期間が長いため、市場の短期的な変動に対するリスク許容度が高くなります。多少の価格変動があっても、長期的な時間の中で回復する機会が十分にあるため、より積極的な投資戦略を取ることができます。
さらに、iDeCoには現役時の所得控除というメリットがあります。給与所得が低い若いうちから始めることで、所得控除による節税効果を長期間享受できます。新NISAは非課税投資期間が実質無期限となり、早期に投資を始めることで非課税メリットを最大限に活用できます。

投資を始める前に基本的な用語の意味を理解しておくことで、より適切な投資判断が可能になります。特に始めて間もない方は、投資信託の基本用語と投資戦略に関する用語から理解を深めていくことをお勧めします。
1. 投資信託の基本用語
2. 株式投資の基本用語
3. 投資戦略に関する用語
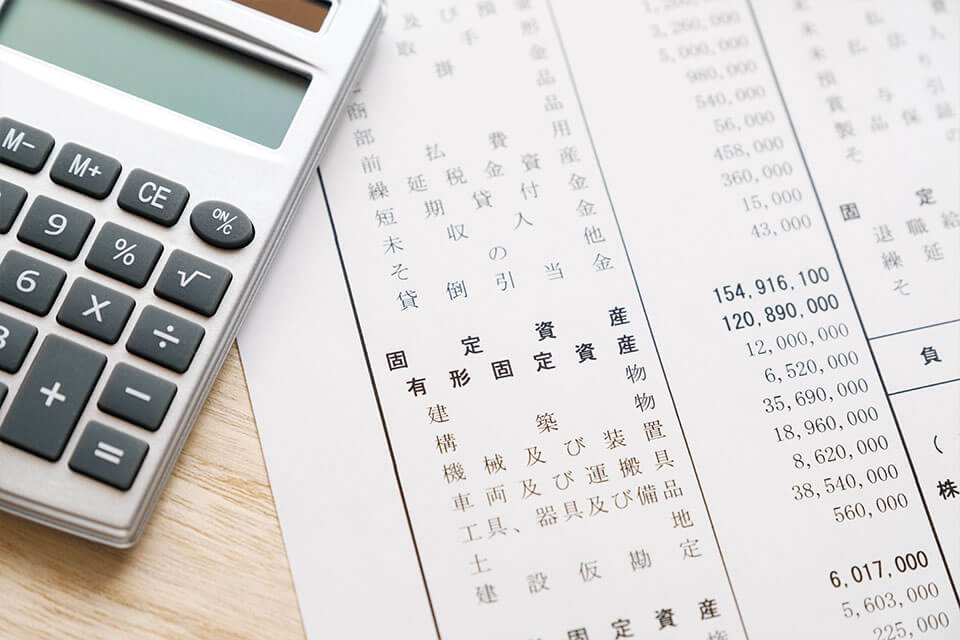
決算書とは、企業の財務状況と経営成績を示す重要な財務諸表です。主に「貸借対照表(BS:Balance Sheet)」、「損益計算書(PL:Profit and Loss statement)」、「キャッシュフロー計算書(CF:Cash Flow statement)」の3つの書類(三表)で構成されています。
貸借対照表(BS)のチェックポイント
損益計算書(PL)のチェックポイント
キャッシュフロー計算書(CF)のチェックポイント
生活に密着したお金のエキスパート「FP(ファイナンシャルプランナー)」資格の学習がおすすめです。
暮らしに必要な資金を有効活用するだけでなく、資産運用や金融商品を提案する銀行、証券会社、保険会社での仕事にも役立ちます。
また資格の大原FP講座のパンフレット(冊子またはPDF)をご覧になりたい方は、ぜひ以下のリンクよりご確認ください。