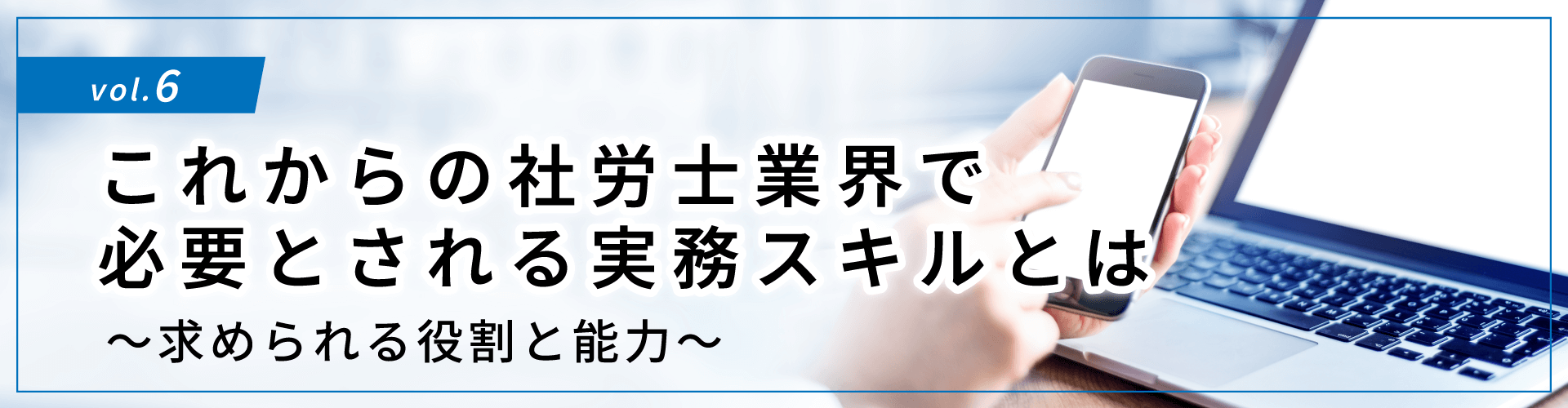
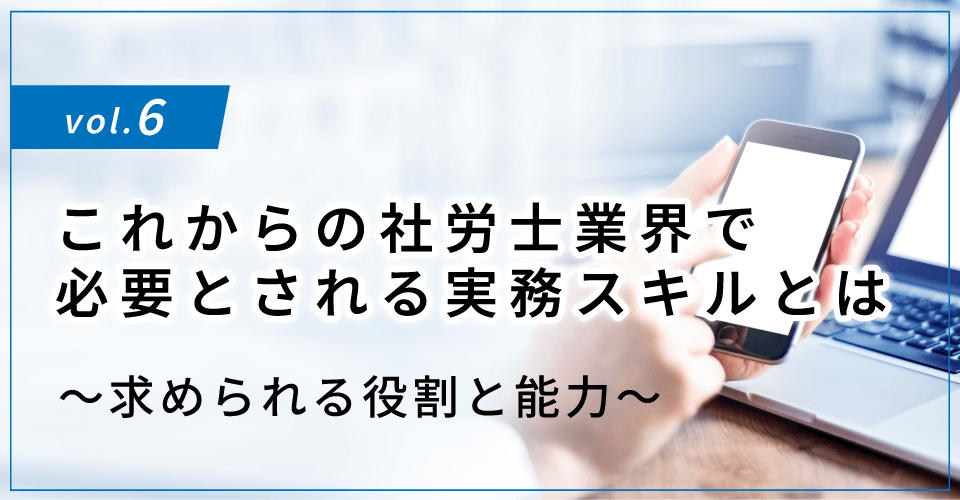
資格の大原による、お役立ち情報をお届けするコラムシリーズです。
(公開:2024.10.11)

社会保険労務士(社労士)は、労働や社会保険に関する専門家として、企業や個人に重要なサービスを提供しています。しかし、急速に変化する社会情勢や技術革新により、社労士に求められる役割や能力も変化しつつあります。本コラムでは、これからの社労士業界で必要とされる実務スキルについて、業界の現状分析から具体的なスキルの提案まで、幅広い視点から解説します。

社労士業界は、近年、様々な変化に直面しています。少子高齢化、働き方改革、デジタル化の進展など、社会構造の変化に伴い、社労士の役割も拡大・多様化しています。そんななか、社労士の登録者数は年々増加傾向にあり、競争は激化しています。
従来の労務管理や社会保険手続きに加え、人事戦略立案や経営コンサルティングなど、より広範な分野へのサービス提供が求められており、働き方改革関連法や社会保険制度の改正など、頻繁な法改正に迅速に対応する必要性も高まっています。また、電子申請システムの普及や、クラウド型人事労務システムの台頭により、従来の事務作業の自動化が進んでいます。このため、社労士には、より高度な専門知識と、デジタルツールを活用する能力が求められるようになっています。

社労士の役割は、労働環境や社会保障制度の変化に伴い、常に進化を続けています。特に、法人分野と障碍者雇用分野においては、近年急速な変化が見られ、新たな機会が生まれています。
企業の労務管理は、2018年に成立した働き方改革関連法により、大きな転換点を迎えました。長時間労働の是正、有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金の導入などが挙げられますが、それに伴う労働時間管理システムの導入支援や就業規則や賃金規定の見直しコンサルティング、中小企業向けの段階的な制度導入サポートといったニーズが生まれています。また、コロナ禍をきっかけに、テレワークやフレックスタイム制の普及、副業・兼業の増加など、働き方の多様化が進んでいます。テレワーク導入に伴う労務管理のアドバイスや新しい雇用形態に対応した人事制度の設計、副業・兼業に関する社内規定の整備支援などが社労士に求められています。
さらに、近年はメンタルヘルス対策の義務化や健康経営優良法人認定制度の普及など、従業員の健康管理が企業の生産性向上や人材確保に直結するという認識が高まっています。そのため、ストレスチェック制度の導入・運用支援や健康経営優良法人認定取得のコンサルティング、従業員の健康増進施策の立案・実施サポートといったことも社労士が対応すべき項目として挙げられます。
2020年6月にはパワーハラスメント防止措置が義務化しました。セクハラ・マタハラ対策の強化など、企業のハラスメント対策がより重要になっています。ハラスメント防止規程の整備や管理職向けハラスメント防止研修の実施、ハラスメント相談窓口の設置・運営支援などが求められています。
法定雇用率の段階的引き上げや、精神障碍者の雇用義務化などといった法の改正により、企業の障碍者雇用に対する取り組みが強化されています。そうしたなか、障碍者雇用計画の立案支援や職場環境のバリアフリー化アドバイス、障碍者の職場定着支援プログラムの開発を求める企業も増えています。
また、発達障害に対する社会的認知の向上に伴い、発達障碍者に対する支援ニーズも高まっています。発達障碍者の特性に応じた職務設計、職場における理解促進のための研修、発達障碍者向けキャリア開発支援などを求める企業も増加傾向にあります。このように、障害分野では医療・福祉の知識に加え、きめ細やかな個別対応能力が重要になります。

近年のAI技術の発展により、社労士の業務にも大きな変化が訪れています。給与計算や社会保険料の自動計算、各種申請書類の作成支援、法令や判例のデータベース検索・情報提供などといった定期的な業務はAIが効率化してくれます。一方、人間の社労士には、複雑な労務問題に対する解決策の提案や、経営戦略と連動した人事制度の設計、メンタルヘルスや職場環境改善などの従業員支援、クライアントとの信頼関係構築とコミュニケーションなど、高度な判断や対人スキルを要する業務が求められるようになっています。
社労士には今後、AIツールを効果的に活用しつつ、人間にしかできない創造的で共感的な業務に注力することが重要になってきます。そのため、デジタルリテラシーの向上と同時に、コンサルティング能力や対人コミュニケーションスキルの磨き上げが不可欠です。AIと協調しながら、より付加価値の高いサービスを提供できる社労士が、これからの業界には求められています。

これからの社労士には、多岐にわたる実務スキルと独立経営スキルが求められます。実務面では、労働法制や社会保険制度に関する専門知識はもちろん、デジタルリテラシーが不可欠です。具体的には、クラウド型人事労務システムの活用能力やデータ分析スキルが重要となります。また、問題解決力やコンサルティング能力も欠かせません。クライアントのニーズを的確に把握するヒアリング力、効果的な解決策を提案するプレゼンテーションスキル、そして複雑な労務問題に対する実践的な問題解決能力が求められます。
独立経営を目指す社労士には、これらの実務スキルに加えて、経営戦略立案能力やマーケティング能力が必要です。市場分析に基づく差別化戦略の策定、効果的な広報・営業活動の展開が鍵となります。さらに、財務管理能力も重要で、適切な価格設定や資金繰りの管理が求められます。ネットワーキング能力も欠かせず、他の専門家との連携や業界団体との関係構築が必要です。さらに、継続的学習能力とイノベーション力も重要とされています。最新技術や制度変更への適応、新しいサービス開発への取り組みが、これからの社労士の成功を左右するでしょう。

社労士業界は大きな転換期を迎えています。AIやデジタル技術の進展により、従来の業務の多くが自動化される一方で、より高度な専門性と、人間ならではの洞察力や創造性が求められるようになっています。
これからの社労士には、専門知識を深めつつ、デジタルツールを活用し、クライアントの真のニーズに応える総合的なサービスを提供することが期待されています。また、独立開業を目指す場合は、経営者としての視点も重要になります。
継続的な学習と実践を通じて、これらのスキルを磨き上げることで、変化の激しい時代においても、社労士は企業と個人の「人」に関する課題解決のキーパーソンとして、ますます重要な役割を果たしていくことができるでしょう。
毎年多くの合格者を輩出している資格の大原での学習がおすすめです。
資格の大原社労士講座のパンフレット(冊子またはPDF)をご覧になりたい方は、ぜひ以下のリンクよりご確認ください。