
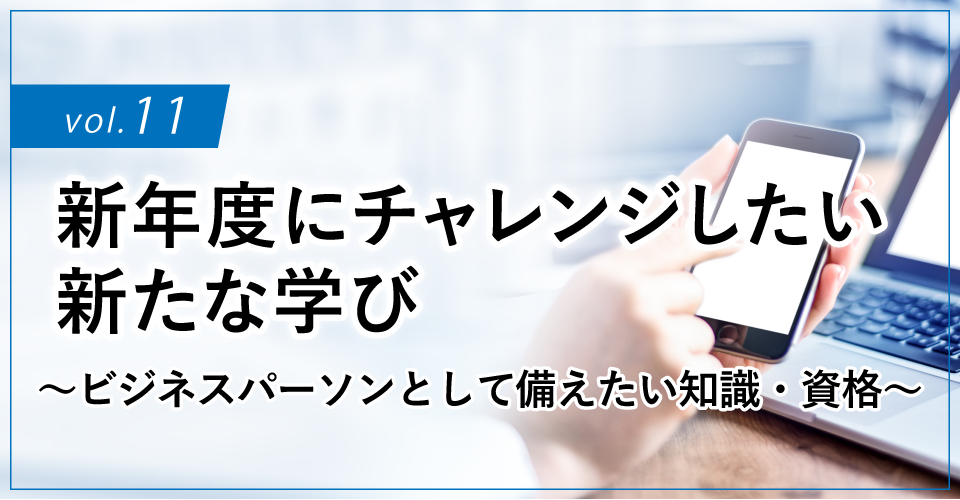
資格の大原による、お役立ち情報をお届けするコラムシリーズです。
(公開:2025.03.21)

春の訪れとともに新年度を迎える季節は、多くのビジネスパーソンにとって新たな目標設定と自己成長を見つめ直す絶好の機会です。AI技術の台頭やグローバル化の深化、働き方の多様化など、私たちを取り巻く環境は刻一刻と変化しています。こうした変革の波に乗り遅れないためには、「リスキリング」が不可欠となっています。
しかし、忙しい日常の中で新たな学びに時間を割くことは容易ではありません。仕事と私生活のバランスを保ちながら、いかに効率的かつ効果的に自己成長を遂げるか。それは多くのビジネスパーソンが抱える共通の課題です。本コラムでは、単に資格取得にとどまらない、実践的な知識やリテラシー向上に焦点を当て、各自のライフスタイルや目標に合わせた学びの道筋を探ります。

現代のビジネス環境では、キャリアを通じて継続的に学び続けることが成功への鍵となっています。しかし、日々の業務や私生活との両立は、多くの人にとって容易ではありません。特に新社会人や、これから就職を控えた大学生にとって、「どうすれば効果的に学びを生活に取り入れられるのか」という問いは切実なものでしょう。
学びを継続するためには、自分のライフスタイルや学習傾向に合った方法を選ぶことが重要です。朝型の人なら早起きして仕事前の静かな時間を活用する、通勤時間を有効活用したい人ならオーディオブックやポッドキャストに耳を傾ける、集中して学びたい人なら週末に数時間のまとまった時間を確保するなど、自分のリズムに合わせた学習習慣を構築しましょう。
継続するコツは、「1日30分」「週に2回」など、具体的かつ達成可能な小さな目標から始めることです。完璧を求めすぎず、時には5分だけでも学びの時間を持つという姿勢が大切です。スマートフォンのリマインダー機能やアプリを活用して習慣化を助けるのも効果的です。
また、可能であれば、日々の業務と学習内容を関連付けることで、より実践的な理解が深まります。新しく学んだ知識やスキルを実際の仕事で試してみるなど、相乗効果を生み出す工夫をしましょう。就職前の学生の方は、インターンシップやアルバイトでの経験と授業で学ぶ内容を結びつける視点を持つことが役立ちます。
学びの過程では、目に見える成果が出るまで時間がかかることもあります。小さな進歩や継続できている事実そのものを自ら認め、自分を褒める習慣を持ちましょう。学習記録をつけることで、振り返った時に自身の成長を実感できます。
仕事と学びの両立は決して容易ではありませんが、自分のペースで無理なく続けることが何よりも大切です。今日からできる小さな一歩を踏み出すことが、将来の大きな飛躍につながります。

資格取得は多くのビジネスパーソンが自己啓発の一環として検討するものですが、ただ資格を持つこと自体が目的になってしまうと、せっかくの努力が実を結ばないことも少なくありません。資格取得を検討する際は、その目的を明確にし、取得後の活用方法まで見据えることが重要です。
資格取得を目指す前に、「なぜこの資格が必要なのか」を自問してみましょう。キャリアアップのためか、特定の業務に必要なスキルを証明するためか、あるいは新たな分野へのチャレンジの足がかりとしてか。目的が明確であれば、学習のモチベーション維持や、取得後の活用方法も自ずと見えてきます。大学生の方は、就職活動での差別化だけでなく、将来のキャリアパスを見据えた資格選びを心がけましょう。
資格取得の真の価値は、合格証書だけでなく学習過程で得られる知識や視点にあります。試験対策だけに終始せず、学んだ内容を日々の業務に積極的に応用してみることで、理解が深まり実践的なスキルとして定着します。学生の方も、アルバイトやインターンシップなどの場で学びを活かす意識を持ちましょう。
肝心なのは資格を取得しただけで終わらせないことです。社内で新たな役割や責任を引き受ける、獲得した知識を基に業務改善を提案する、同じ資格に興味を持つ同僚のメンターとなるなど、積極的に活用する機会を作りましょう。また、資格を通じて得たネットワークを大切にすることも、長期的なキャリア形成に役立ちます。
資格取得は、学びの終着点ではなく、新たな学習サイクルの始まりとして捉えることが重要です。取得した資格を足がかりに、より専門的な知識を深めたり、関連分野へと学びを広げたりすることで、持続的な成長が可能になります。

ビジネスパーソンとして活躍するために、専門分野に関わらず身につけておきたい基礎知識があります。特に情報IT、会計税務、労務法務の3分野は、どのような業種・職種でも役立つ普遍的な知識です。これらを基本レベルで理解しておくことで、業務の幅が広がるだけでなく、多様な視点からビジネス課題を捉えることが可能になります。
情報IT分野では、デジタルリテラシーの基礎が不可欠です。Microsoft Officeなどのビジネスツールはもちろん、データ分析の基本スキル、情報セキュリティの知識などが求められます。近年ではAI・機械学習の基礎概念や、ChatGPTなどの生成AIツールの活用法を理解していることも強みになります。プログラミングの基礎(HTMLやPythonなど)を学ぶことで、業務自動化や効率化のアイデアも生まれやすくなります。大学生のうちから、これらのツールに慣れ親しんでおくことは大きなアドバンテージとなるでしょう。
会計税務の分野では、財務三表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書)の読み方、基本的な税金の仕組み、予算管理の考え方などを押さえておきましょう。数字を通して組織の健全性を判断できる能力は、昇進やキャリアアップの際に重宝されます。また、個人としての資産形成や確定申告の知識も、ライフプランニングの観点から重要です。簿記検定や、FP(ファイナンシャルプランナー)資格などは、この分野の体系的な知識を得るのに役立ちます。
労務法務に関しては、労働基準法や契約の基本、知的財産権などの基礎知識が求められます。コンプライアンスの観点から「やってはいけないこと」を理解するだけでなく、法的な枠組みを活用して「何ができるか」を考える発想も大切です。社会人になると直面する年金や社会保険の仕組みについても、自身の権利を守るために基本は理解しておきましょう。 これらの知識は、一度に全てを習得する必要はありません。日々の業務やニュースに触れる中で関心を持ったトピックから少しずつ学び、徐々に知識の幅を広げていくアプローチが現実的です。オンライン学習プラットフォームや無料のウェビナー、YouTubeの教育チャンネルなど、気軽に学べるリソースも豊富にあります。
大切なのは、これらの知識を「点」ではなく「線」でつなげる視点を持つことです。例えば、IT技術を活用して会計業務を効率化する、あるいは法務知識を踏まえた上でデジタルマーケティングを展開するなど、分野を横断する発想が今後のビジネスでは一層重要になってくるでしょう。
長年にわたり多くの合格者を輩出している資格の大原が提供する、タイパ抜群の通信講座「パススル」がおすすめです。講義動画はテーマ別で5~10分程度にまとめられており、移動時や仕事・家事などのスキマ時間に、スマホで気軽に視聴できるようになっています。また学習スケジュールの自動生成や個人カルテによる弱点把握など、サポート機能も充実しています。詳細はぜひ以下のリンクよりご確認ください。
パススル ブランドイメージ動画(30秒)